ホームページの改善は、事業の成功に欠かせません。
しかし、どのように改善すれば効果的なのか迷っている運用担当者も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、ホームページ改善のための7つのステップと、運用担当者が知っておくべき重要な25のポイントを詳しく解説します。
具体的な改善方法を知ることで、自社のホームページをさらに魅力的で効果的なものにできるでしょう。
ホームページの改善に取り組む運用担当者様は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の内容
成果につながるホームページ改善7ステップ

成果につながるホームページ改善の7ステップは、以下の通りです。
- 改善目的を明確化する
- サイトの現状を把握・分析する
- 課題点を発見する
- 改善案を洗い出す
- 改善施策の優先順位を決定する
- 改善施策を実行する
- 効果検証・改善する
改善目的を明確化する
ホームページ改善の重要なステップとして、まずは改善目的を明確にしましょう。
目的が明確でないまま進めても期待できる効果は見込めません。
ホームページ改善の主な目的は以下の通りです。
- 問い合わせ件数の獲得・アップ
- ブランディング
- 企業や商品・サービスの認知度向上
- 商品の購入数アップ
- 新規顧客の獲得
- リピート顧客の獲得
- 資料請求・ダウンロード
- リードの獲得など
具体的な目的を設定することで、改善の方向性や具体的な取り組みが明確になります。
サイトの現状を把握・分析する
現状のホームページを把握し、データを分析しましょう。
ホームページを改善する前に、現状の課題や改善の必要性を理解しなければいけません。
アクセス解析やユーザーフィードバックを活用して、現状のユーザー行動やユーザーのニーズを把握しましょう。
具体的な数字やデータに基づいた分析結果を見て、現状の問題点や改善のポイントが明確になります。
課題点を発見する
現状分析を通じて、ホームページの課題点を発見しましょう。
課題点を明確にしなければ、改善策を考案できません。
例えば、コンバージョン率が低いのか、そもそもアクセス数やページビュー数(PV)が少ないのかによって、やるべき対策は異なります。
解析ツールを導入して、具体的な数値やデータを用いつつ、読者の意見やフィードバックを取り入れて課題を明確にしましょう。
改善案を洗い出す
課題点を特定したら、改善案を洗い出しましょう。
例えば、コンバージョン率が低いなら、以下のような改善案が考えられます。
- ファーストビューでターゲットに的確な訴求に変更する
- CVの位置とクリックしたくなるようなコピーに改善する
- 入力フォームの項目に無駄を無くす
また、リピート訪問率が低いなら、コンテンツのタイトル変更やUI・UXの改善が視野に入るでしょう。
このように、現状の課題を解決するための案を出してみてください。
改善施策の優先順位を決定する
改善案を洗い出したら、優先順位を決定しましょう。
優先順位を設定することによって、改善の優先度や重要度の把握が可能です。
優先順位は、改善の影響度やコスト、実施可能性など具体的なデータや理由を考慮して決めます。
例えば、ユーザー離脱率の高いページや売上への影響が大きい箇所を優先することで、改善の効果を最大化できるでしょう。
優先順位の決定によって、改善の必要性と順序を決めやすくなります。
改善施策を実行する
優先順位が決まったら、改善施策を実行します。
スムーズな実行をするために、具体的なアクションプランの策定が大切です。
例えば、改善施策のスケジュールや必要なリソース、担当者の役割分担などを明確にしましょう。
効果検証・改善する
改善施策を実施した後は、効果を検証します。
効果検証によって、ホームページの改善成果を確認できます。
さらに、効果のあった施策を把握しておくことで、今後の施策にも活用できるでしょう。
アクセス解析やユーザーフィードバックなど具体的なデータを活用して、改善の効果を評価します。
もし、改善策を実施して効果が得られなかった場合、別の仮説を立てて再度検証してみましょう。
成果につながるホームページ改善のポイント10選

では、成果につながるホームページ改善をする10のポイントをご紹介します。
- ユーザビリティの高いUXにする
- サイトのSEO対策やMEO対策を実施する
- モバイルフレンドリーなサイトにする
- Webサイトの表示速度を高める
- ユーザーニーズを満たすコンテンツ制作・改善をする
- ユーザーが分かりやすい回遊導線を設置する
- 事例を掲載する
- フォームやQ&AなどのEFO対策をする
- ユーザーの関心を引きつけるオファー改善をする
- ホームページとシステムの連携で業務効率化を図る
ユーザビリティの高いUXにする
ユーザビリティを高めるためには、使いやすいユーザーエクスペリエンス(UX)を提供することが重要です。
サイト内でスムーズに目的の情報を見つけられないと、ユーザーはストレスを感じるでしょう。
企業や商品・サービスのイメージは「使いづらそう……」と評価を下げかねません。
ナビゲーションの改善、情報の整理、わかりやすいコンテンツ配置など、ユーザーがサイトをスムーズに操作できるように工夫しましょう。
サイトのSEO対策やMEO対策を実施する
SEO対策やMEO対策は、ユーザーがホームページを見つけやすくするための重要な取り組みです。
検索エンジンでの上位表示やモバイル検索での最適化などによって、企業のWebプレゼンスが強化されます。
より多くの読者が企業のホームページにアクセスし、企業のサービスや製品に関心を持つ可能性が高まるでしょう。
検索エンジンに評価されるためには、キーワードの適切な選定、メタデータの最適化、モバイルフレンドリーなデザインなどが重要です。
モバイルフレンドリーなサイトにする
ホームページは、必ずモバイルフレンドリーにしましょう。
そもそも、モバイルフレンドリーとは、スマートフォンで閲覧した時の表示を最適化することです。
総務省の調査によると、個人の端末別インターネット利用率は、「スマートフォン」が68.5%、「パソコン」が48.1%と公表されました。この調査結果から、スマートフォンの使用率が高いことが分かるでしょう。
レスポンシブデザインの採用やモバイル専用のレイアウト設計によって、ユーザーは快適にサイトを閲覧できます。
ユーザーエクスペリエンスの向上にもつながり、サイトの評価を高められます。
Webサイトの表示速度を高める
Webサイトの表示速度は、ユーザーエクスペリエンスやSEOに影響を与える重要な要素です。
サイトの表示速度が遅いホームページは、ユーザーにとってストレスとなります。
中々表示されないとブラウザバックされやすく、離脱率の上昇にもつながりかねません。
Webサイトの表示速度を高めるために、画像の最適化、キャッシュの活用、コードの最適化などの手法を取り入れましょう。
高速な表示速度はユーザーの満足度を高めて、ページの滞在時間を延ばす効果があります。
ユーザーニーズを満たすコンテンツ制作・改善をする
ユーザーのニーズを的確に把握し、そのニーズに合わせたコンテンツを提供しましょう。
コンテンツは、ユーザーが求める情報や解決したい課題に応えることが重要です。
ユーザーフィードバックやデータ分析を活用して、コンテンツを考えましょう。
また、定期的な改善を行い、コンテンツの質を向上させることで効果を最大化できます。
ユーザーからの信頼性を獲得して、自社の商品やサービスの評価も高められるでしょう。
ユーザーが分かりやすい回遊導線を設置する
ユーザーがサイト内をスムーズに移動できるような回遊導線を設置しましょう。
ホームページは、ユーザーが必要な情報に迅速にアクセスできることが重要です。
メニューの整理や内部リンクの活用、関連コンテンツの提供などの環境を整えましょう。
分かりやすい導線が設置されていると、ユーザーは行動しやすくなり、回遊率やコンバージョン率の向上が期待できます。
事例を掲載する
事例を掲載することにより、ユーザーに対して自社の製品やサービスの実績や信頼性をアピールできます。
自社の製品やサービスを利用した顧客の成功事例や利用した生の声などを掲載しましょう。
こうした具体的な数値やデータは、ユーザーへの安心感や信頼度アップにつながります。
フォームやQ&AなどのEFO対策をする
フォームやQ&AなどのEFO(Effective Field Order)対策を行いましょう。
EFO対策とは、ユーザーが登録やお問い合わせフォームの入力をストレスなく行えて、スムーズにコンバージョン先に遷移するための施策です。
いくらコンテンツ内容やデザインが良くても、最終的な行動に踏み出せなければコンバージョン率は高まりません。
ユーザーの利便性と満足度を高めるために、ユーザーがアクションを起こしやすいフォームを構築しましょう。
ユーザーの関心を引きつけるオファー改善をする
ユーザーの関心を引きつける魅力的なオファーを提供することで、コンバージョン率を向上できます。
割引クーポンや限定特典、無料コンテンツなど、ユーザーにとって価値のあるオファーを改善しましょう。
オファーは、ユーザーへのベネフィットをシンプルかつ魅力的に伝えることが大切です。
コピーや表現方法に工夫を凝らし、読者が瞬時に理解できるようにしましょう。
また、具体的な数値や事例、成功体験などを交えることで、ユーザーへの説得力を高められます。
自社の製品やサービスに対する関心を高めることで、ユーザーもアクションを起こしやすくなるでしょう。
ホームページとシステムの連携で業務効率化を図る
ホームページ運用は、CRMや日程調整ツール、MAツールなどの外部システムと連携させると、業務効率化と成果向上を図れます。
特に、CRM(顧客管理ツール)との連携は、ホームページ上の顧客行動データを自動的にシステムに蓄積させ、リアルタイムで見込み顧客の関心度を把握するのに便利でしょう。
日程調整ツールでは、相談会やセミナーの申し込みページから直接予約システムに接続すると、ユーザーは空き状況を確認しながら予約を完了できます。企業側も、予約管理に時間と労力をかける必要はありません。
これらのシステム連携は、顧客満足度の向上と担当者の作業負荷軽減を同時に実現できるので、導入を検討してみてもよいでしょう。
ホームページへのアクセス数改善につながる手法4個

ホームページのアクセス数を増やすには、検索エンジンとユーザーの両方に評価されるサイト作りが重要です。
具体的には、以下に示す4つの手法を実践しましょう。
- キーワードをタイトルや大見出しに入れる
- 専門用語を減らしてニーズ寄りの言葉に変える
- SEOのマイナス要因を排除する
- 被リンクを意識して外部からの評価を得る
キーワードをタイトルや大見出しに入れる
検索エンジンがサイトの内容を理解するために、重要な要素がタイトルタグ(title)と大見出し(h2)です。
効果的なキーワード配置のポイント
- キーワードをタイトルの前半に配置する
- 大見出し(h2)の前半にキーワードを組み込む
- 地域情報や特徴を含めて差別化を図る
また、各ページでタイトルに沿った説明文(meta description)を設置すると、クリック率の改善にもつながります。
ホームページのタイトルを決めるコツは、こちらの記事を参考にしてみてください。
 ホームページタイトルの付け方!SEOやサイトのクリック率を高めるコツ
ホームページタイトルの付け方!SEOやサイトのクリック率を高めるコツ
専門用語を減らしてニーズ寄りの言葉に変える
業界の専門用語は、その分野の関係者には馴染み深い言葉でも、一般ユーザーには理解が困難な場合があります。
そこで、検索ボリュームを調査し、実際にユーザーが使うキーワードに置き換えると、より多くの見込み顧客へリーチが見込めるでしょう。
業界常識にとらわれず、ユーザー視点でのキーワード選定を心がけてみてください。
SEOのマイナス要因を排除する
SEOの改善効果を最大化するには、マイナス要因の排除が欠かせません。
主なマイナス要因と対策
| SSL未対応への対処 | HTTPからHTTPSへの切り替え 無料SSL証明書サービスの活用 セキュリティ向上による信頼性アップ |
|---|---|
| URLの重複問題解決 | 301リダイレクトによる正規URL統一 canonicalタグでの重複ページ指定 「www.あり/なし」の統一設定 |
SSL未対応のサイトは、セキュリティ面でリスクがあり、検索エンジンから低評価を受けかねません。
また、URLの重複は検索エンジンからの評価に関わるので、必ず解消しておきましょう。
被リンクを意識して外部からの評価を得る
被リンクは、検索エンジンが「信頼できるサイト」と判断する大きな要素です。
獲得方法には、以下のようなものがあります。
- 自社の他サイトからリンクを設置
- 他社メディアへの寄稿やプレスリリース配信
- 価値あるコンテンツ発信による自然なリンク獲得
これらを組み合わせると、長期的なアクセス数の向上が期待できるでしょう。
ホームページの離脱率改善につながる手法4個

ホームページの離脱率改善につながる手法は、以下の4つです。
- アピール文や関連性の高いビジュアルをファーストビューに配置する
- ユーザーの関心度をもとにコンテンツの順番と量を最適化する
- ストレスなく回遊できるページ内ナビゲーションを設置する
- 視認性を高めるために図解を活用する
アピール文や関連性の高いビジュアルをファーストビューに配置する
まず、ファーストビュー(スクロールせずに見える画面上部)を改善します。
具体的には「メリットを数値で示すアピール文」を配置するとよいでしょう。
たとえば「お客様満足度◯%」「導入実績〇〇社」などの定量的データは、信頼獲得に直結します。また、サービス内容が一目で理解できる関連性の高い画像や図を組み合わせると、視覚的な理解を促進できるでしょう。
ファーストビューは「何を提供する会社なのか」「なぜ選ぶべきか」を瞬時に伝える重要な役割があります。
具体的な設計ポイントやデザインのコツは、こちらの記事を参考にしてみてください。
 ファーストビューとは?7つの設計ポイントやデザインの参考事例を紹介
ファーストビューとは?7つの設計ポイントやデザインの参考事例を紹介
ユーザーの関心度をもとにコンテンツの順番と量を最適化する
ユーザーが関心度の高いコンテンツを上部に配置し、内容を充実させると、滞在時間の延長につながります。
たとえば、サービス紹介ページで「価格情報」への注目度が高いことが判明した場合、料金表をページ上部に移動させるとよいでしょう。
また、ユーザーが求める情報と実際のサイト構成にズレがある場合は、ターゲット層の再定義も必要です。
また、ユーザーの関心度を測るには、ヒートマップツールを活用すると、注目されやすいページや、離脱の発生ポイントを分析できます。
コンテンツの順番は、ユーザーの関心を引くのに欠かせません。
具体的なサイト設計の手順は、こちらの記事を参考にしてみてください。
 サイト設計とは?重要性や正しいやり方・おすすめツール5選を紹介
サイト設計とは?重要性や正しいやり方・おすすめツール5選を紹介
ストレスなく回遊できるページ内ナビゲーションを設置する
ユーザーがストレスなく情報にアクセスできるナビゲーション設計も、離脱率改善につながります。
情報量の多いページでは「どこに何が書いてあるか分からない」「欲しい情報に辿り着けない」などの理由で、離脱が発生します。
効果的なページ内ナビゲーション設定のコツ
- 冒頭に目次を設置し構成を一目で理解できるようにする
- 各セクションへのジャンプ機能を提供する
- 固定ヘッダーにナビゲーションメニューを配置する
ナビゲーションの改善は、ユーザーの回遊性向上と離脱率改善の両方に効果的です。
モバイルでも問題なく表示できるよう、徹底してください。
視認性を高めるために図解を活用する
テキスト中心のコンテンツは、ユーザーにとって理解しづらく、離脱の原因になります。
そこで、図解やビジュアル要素を効果的に活用して視認性を高め、滞在時間の延長につなげましょう。
効果的な図解活用のポイント
- サービスの導入フローを図解化する
- 料金体系を表やグラフで示す
- 重要な箇所はフォントやカラーを変えてメリハリをつける
重要な情報を視覚的に強調し、視認性を高めてみてください。
ホームページからの誘導につながる改善手法3個
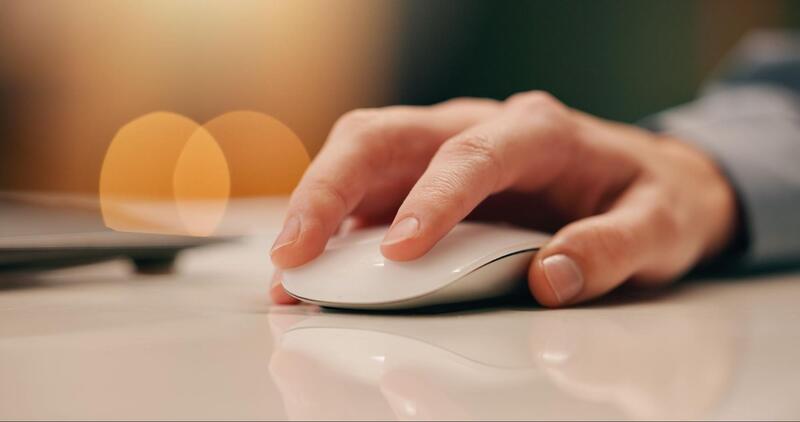
ホームページからの誘導につながる改善手法は、以下の3つです。
- フッターに追従型のボタンを表示する
- ページの文脈に合った誘導を自然に設置する
- ファーストビューに相談会やイベント情報を掲載して関心を引く
フッターに追従型のボタンを表示する
ユーザーは、必ずしも画面下部までスクロールして閲覧するとは限りません。
その場合、ページ内の特定箇所にのみ問い合わせボタンを配置していると、誘導機会を逃してしまうでしょう。
この問題を解決するのが、追従型ボタン(スティッキーボタン)の導入です。
これは、画面下部に常時表示されるボタンで、ページのどこを閲覧していても、瞬時にアクションを促せます。
ユーザーが長い説明を読み進める中で「詳しく知りたい」と感じた瞬間に、自然に誘導できるでしょう。
ただし、ボタンのサイズが大きすぎると画面を圧迫し、逆にユーザビリティを損ないます。
スマートフォンでの表示を考慮し、コンテンツの邪魔にならないサイズで設置しましょう。
ページの文脈に合った誘導を自然に設置する
効果的な誘導を促すには、コンテンツの流れに沿った自然な誘導設置が欠かせません。
たとえば、料金に関するページでは「プランの詳細はこちら」のように、料金に関連する誘導が効果的です。
一方で、同じページに「お問い合わせはこちら」という一般的な誘導を置いても、ユーザーの心理状態とミスマッチが生じ、クリック率は低くなるでしょう。
ページ全体のストーリー性を意識し、訪問者が自然に次のステップに進みたくなるような導線設計を心がけてください。
ファーストビューに相談会やイベント情報を掲載して関心を引く
ファーストビューにタイムリーな情報を配置すると、ユーザーの緊急性を高め、具体的な行動につなげられます。
特に「今だけ無料相談可能!」「期間限定セミナー」などの情報は、明確な期限があるため、決断を後押しする誘導要素になるでしょう。
また、効果的なイベント情報の掲載には、日程の明示が重要です。
「近日開催予定」といったあいまいな表現ではなく「〇月〇日開催」「あと3席」などの具体的な情報により、必要性を感じてもらいやすくなります。
緊急性と価値を組み合わせたタイムリーな情報発信で、ユーザーの行動を効果的に促しましょう。
ホームページからのCVにつながる改善手法4個

ホームページからCVにつながる改善手法は、以下の4つです。
- ハードルの低い成果地点を設けて段階的なCVをつくる
- ターゲットに合わせた誘導先を設計する
- フォームの利便性を高める
- ユーザーを後押しするマイクロコピーをつける
ハードルの低い成果地点を設けて段階的なCVをつくる
いきなり契約を求める高いハードルの誘導では、多くの潜在顧客を取りこぼしてしまいます。効果的なCV向上策として、ユーザーの心理状態に応じた段階的なアプローチを設計しましょう。
成果地点として効果的な手法
- 無料診断・相談
- オンライン見積もり
- 資料請求
- 事例集ダウンロード(ホワイトペーパーのダウンロード)
これらはユーザーにとって価値があり、かつ個人情報提供への抵抗感が少ないので、初回接触の成功率が高くなります。
一度の訪問で成果を求めるのではなく、継続的な関係性構築を前提とした戦略を設計してみてください。
ターゲットに合わせた誘導先を設計する
ターゲット層の特性や商材の性質に応じた、最適な誘導先の設計も重要です。
世代や業界、検討段階によって好まれるコミュニケーション手段は異なります。簡易的な問い合わせフォームだけでは、機会を損失しかねません。
年代別の傾向として、シニア層なら電話での相談を好みやすく、若年層ではチャットやLINEで気軽さを選ぶ人が多いでしょう。
最適な誘導先を設計するには、顧客ターゲット層の明確化が欠かせません。
行動パターンや情報収集方法を分析したうえで、複数パターンを用意してみてください。
フォームの利便性を高める
フォームまで到達したユーザーは、購入意欲が高い貴重な存在です。入力途中での離脱を防ぐため、フォームの利便性を高めてください。
フォーム改善の基本として、以下のポイントを押さえましょう。
- 入力項目は必要最小限に絞る
- 必須項目を埋めるまで「送信」ボタンを非アクティブに設定する
- リアルタイムのエラーチェックを表示する
- 郵便番号入力で住所を自動補完させる
- 電話番号入力時の数字キーボードを自動表示させる
特にスマートフォンでの入力を考慮し、タップしやすいボタンサイズや適切な入力フィールドサイズを設定しましょう。
これらの改善により、フォーム完了率の向上とCV数増加を見込めます。
ユーザーを後押しするマイクロコピーをつける
ユーザーを後押しするマイクロコピーも、CV改善に有効な手段です。
マイクロコピーとは、入力フォームやアクションボタン周辺に設置する文章です。
ユーザーがアクションを起こす際の、心理的な不安や迷いを取り除く短い文章を設置すると、CV率改善に効果的でしょう。
効果的なマイクロコピーの種類
- 「1分で完了」「入力は3項目だけ」など、手続きへの不安を軽減させる
- 「お客様満足度◯%」「選ば続けて◯年」などで信頼感を向上させる
- 「今月限定」「残り◯名様」で行動の後押しする
- 「不明点は電話でサポート」「24時間以内に返信」で、後の不安を解消する
- 「相談無料」「資料無料」「キャンセル無料」で、リスクへの懸念を払拭する
小さな工夫ですが、訪問者の心理に直接働きかける強力な改善手法として、積極的に活用しましょう。
まとめ:ホームページを改善して成果に結びつけよう

ホームページ改善は、企業やブランドの信頼性アップや売上の向上につながります。
成果を最大化するためにも、効果のある改善を行いましょう。
また、ホームページ改善は一度で完結しません。
継続的な改善と運用を行うことで、成果の最大化につなげられます。
なお、ワンページ株式会社は、SEOなど集客力の高いホームページ制作が強みの制作会社です。
サイトリニューアルにも対応していますので、ホームページに関する悩みや相談のある方は、ぜひお問い合わせください。









