優秀な人材を獲得するために魅力的な採用サイトを作りたいけれども、制作コストがネックだと悩む企業担当者もいるのではないでしょうか。実は、採用サイトの制作に国や自治体の補助金を活用すれば、費用面の課題を解決できるかもしれません。
そこで本記事では、採用サイトに使える補助金を一覧で紹介し、申請条件・方法もあわせて解説します。本記事を読めば、採用サイトに活用できる補助金を理解してスムーズに申請できます。制作コストを抑えて採用サイトを制作し、優秀な人材の確保に努めましょう。
この記事の内容
採用サイト制作に補助金を利用するメリット

採用サイト制作に補助金を利用するメリットは、大きく以下の2つが挙げられます。
- 制作費用を大幅に削減できる
- 補助金の申請を通して経営計画を見直すきっかけにもなる
特に、費用面がネックで採用サイトの制作に踏み出せない企業は、補助金を積極的に活用しましょう。
制作費用を大幅に削減できる
補助金のメリットは、採用サイトの制作にかかる費用の負担を大幅に軽減できる点です。採用サイトで応募者数の増加など成果を求めた場合、質の高いデザインやコンテンツが必要で制作費用は高額になります。
そのため、制作費用がネックとなって制作をためらったり、内容を妥協してしまったりするケースも少なくありません。
しかし、補助金を活用すれば、国や自治体から制作費用の一部が支援されるため、企業の自己負担を大きく減らせます。
補助金の申請を通して経営計画を見直すきっかけにもなる
補助金での申請プロセスそのものが、企業の経営を見直すきっかけになる点もメリットです。なぜなら、ほとんどの補助金申請では事業計画書の提出が必須であるためです。
事業計画書を作成する過程で自社の現状を客観的に分析し、以下の点を掘り下げて言語化する必要があります。
- 自社の強みは何か
- 今後どのような事業展開を目指すのか
- 事業発展のためには、どのような人材が必要なのか
日々の業務に追われていると、上記のような根本的な問いと向き合う時間はなかなか取れません。補助金の申請手続きを活かして自社の将来像を具体的に描けば、採用すべき人物像がより明確になります。
結果として「誰に」「何を」伝えるべきかがクリアになり、求職者の心に響く訴求力の高い採用サイトが制作できます。
採用サイト制作のお得な補助金1.小規模事業者持続化補助金

出典:小規模事業者持続化補助金
従業員数が比較的少ない、小規模事業者の方におすすめしたいのが「小規模事業者持続化補助金」です。小規模事業者持続化補助金は、事業者が自ら経営計画を作成して行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。
採用サイトを制作して自社の魅力を広く伝え、優秀な人材を確保する行為も販路開拓・生産性向上の取り組みの一環と捉えられる可能性があります。特に、知名度や採用予算で大企業に劣りがちな小規模事業者にとって、小規模事業者持続化補助金は採用力強化の大きな味方となります。
申し込みの必要要件
小規模事業者持続化補助金を申請するためには、小規模事業者であることが第一の要件です。
IT導入補助金よりも対象となる事業者の規模が限定されているため、以下の条件に自社が該当するかをまず確認しましょう。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数5人以下
- 宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数20人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員の数20人以下
引用:小規模事業者持続化補助金
なお、上記の従業員数要件を満たした上で、地域の商工会または商工会議所の支援を受けなければなりません。作成した経営計画書を地域の商工会・商工会議所に提出し、内容の確認とアドバイスを受けた上で事業支援計画書を発行してもらう必要があります。
補助金額
申請する枠によって、補助率や補助上限額が異なります。
| 類型 | 補助率 | 補助上限額 | インボイス特例 (上乗せ) |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 2/3 | 50万円 | あり(+50万円) |
| 賃金引上げ枠※ | 2/3(赤字事業者は3/4) | 200万円 | あり(+50万円) |
| 卒業枠※ | 2/3 | 200万円 | あり(+50万円) |
| 後継者支援枠 | 2/3 | 200万円 | あり(+50万円) |
| 創業枠 | 2/3 | 200万円 | あり(+50万円) |
※賃金引上げ枠・卒業枠は、補助事業終了時点で一定の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は、補助金が交付されません。
なお、採用サイトの制作費は「ウェブサイト等関連費」として扱われ、補助対象経費全体のうち1/4が上限です。
申し込み手順
小規模事業者持続化補助金の申請は、商工会・商工会議所との連携が鍵となり、具体的なステップは以下のとおりです。
| ステップ | 内容・注意点 |
|---|---|
| 1.経営計画書・補助事業計画書の作成 | 自社の強み・課題を分析して販路開拓の計画を立て、採用サイトをどのように活用するのかを具体的に計画書へ落とし込む |
| 2.商工会・商工会議所への相談と計画書交付 | 作成した計画書をもとに、地域の商工会・商工会議所へ相談し、内容の確認を受ける |
| 3.申請書類の提出 | すべての必要書類を揃え、電子申請または郵送で事務局に提出する |
| 4.交付決定と事業の実施 | 審査に通過すると交付決定通知書が届き、通知日以降に補助対象となる事業を開始する |
| 5.実績報告と補助金の請求 | 計画した事業が完了した後、領収書等の証拠書類を添えて実績報告書を提出し、指定口座に補助金額が振り込まれる |
採用サイト制作のお得な補助金2.事業再構築補助金
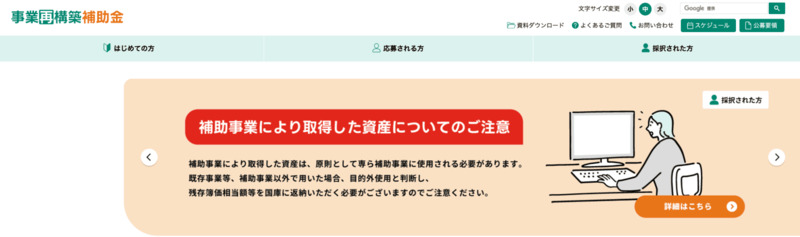
出典:事業再構築補助金
事業再構築補助金は、ポストコロナにおける経済社会の変化に対応するため中小企業等の事業再構築を支援する制度です。
事業再構築補助金は、採用サイトの制作そのものを目的としての申請はできず、あくまで大きな事業転換や新しい分野への挑戦が補助の対象です。そのため、新たな事業を推進するために専門知識を持つ人材が不可欠な場合に、採用サイトの制作費が補助対象に含まれる可能性があります。
申し込みの必要要件
補助金の申請にはいくつかの基本要件が定められており、これらを満たす必要があります。
基本要件
- 事業再構築指針に沿った事業であること
- 事業計画に対して、金融機関や認定経営革新等支援機関の確認を受けること
- 補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年平均成長率が3~4%以上(事業類型により異なる)、従業員1人あたりの付加価値額の年平均成長率が3~4%以上のいずれかを達成すること
申請時には、自社の取り組みがどの類型に該当するのかを明確にし、具体的な数値目標を含んだ事業計画書を作成することが重要です。
また事業計画については、以下の類型から自社の取り組みがどれに該当するかを明確にし、計画を策定してください。
- 新分野展開
- 事業転換
- 業種転換
- 業態転換
- 国内回帰
- 地域サプライチェーン維持・強靱化
たとえば「レストラン経営のみだった企業が、ECサイトで全国向けの冷凍惣菜販売事業をはじめる」などが該当します。
上記の場合、新事業である冷凍惣菜部門のスタッフを募集するための採用サイト制作は、事業再構築の一環とみなされる可能性があります。
補助金額
事業再構築補助金の補助率と補助上限額は、以下のとおりです。
| 類型 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 成⻑分野進出枠 (通常型) |
・従業員数20人以下 1,500万円(※2,000万円) ・従業員数21〜50人 3,000万円(※4,000万円) ・従業員数51〜100人 4,000万円(※5,000万円) ・従業員数101人以上 6,000万円(※7,000万円) 「廃業を伴う場合」は、上限額に最大2,000万円が加算されるケースあり |
中⼩:1/2(※2/3) 中堅:1/3(※1/2)※大規模な賃上げを実施する場合 |
| 成長分野進出枠 (GX進出類型) |
中⼩ ・従業員数20⼈以下 3,000万円(※4,000万円) ・従業員数21人〜50⼈ 5,000万円(※6,000万円) ・従業員数51人〜100⼈ 7,000万円(※8,000万円) ・従業員数101⼈以上 8,000万円(※1億円)中堅 1億円(※1.5億円) ※大規模な賃上げを実施する場合 |
同上 |
| コロナ回復加速化枠 | 5人以下:500万円 6~20人:1,000万円 21人以上:1,500万円 |
中⼩:3/4(※2/3) 中堅:2/3(※1/2) ※借換実施など要件により変動 |
引用:事業再構築補助金
申し込み手順
事業再構築補助金の申請プロセスは、以下のとおりです。
| ステップ | 内容・注意点 |
|---|---|
| 1.認定経営革新等支援機関の選定 | 金融機関やコンサルティング会社など、事業計画の策定を共同で行う認定経営革新等支援機関を見つける |
| 2.事業計画書の策定 | 認定支援機関と綿密な打ち合わせを重ね、事業計画書を策定 |
| 3.電子申請 | 完成した事業計画書を補助金申請システム「Jグランツ」から提出 |
| 4.採択・交付決定 | 審査を通過後、事務局とのやり取りを経て正式な交付決定の通知を受ける |
| 5.補助事業の実施 | 交付決定通知日以降に、補助対象となる事業を開始する |
| 6.実績報告と補助金の支払い | 事業完了後、必要書類を揃えて実績報告し、補助金額が確定した後に指定口座へ振り込まれる |
採用サイト制作のお得な補助金3.地方自治体の補助金・助成金

これまで国が主体となる補助金を紹介しましたが、都道府県や市区町村などの地方自治体が独自に実施している補助金・助成金制度もあります。
以下では、代表的な例として東京都・大阪府・名古屋市の採用サイト制作に活用できる補助金・助成金を紹介します。
東京都で利用できる補助金・助成金
東京都で採用サイト制作の費用が補助対象となる補助金・助成金の一例は、以下のとおりです。
| 市区町村 | 制度名 | 概要・採用サイトとの関連性 |
|---|---|---|
| 荒川区 | ホームページ作成補助金 | 区内の中小企業が販路開拓等を目的としてホームページを作成する際の委託経費を補助 |
| 葛飾区 | ホームページ作成費補助 | 区内の中小企業が日本語または外国語対応のホームページを作成・改修する費用を補助 |
| 港区 | 創業・スタートアップ支援事業補助金 | 創業初期の事業者を対象に広報費の一部としてホームページの作成費を補助 |
| 江東区 | ホームページ作成費補助 | 区内の中小企業が初めて自社ホームページを開設する際、その費用の一部を補助(※リニューアルや過去に開設歴がある場合は対象外) |
大阪府で利用できる補助金・助成金
大阪府で採用サイト制作の費用が補助対象となる補助金・助成金の一例は、以下のとおりです。
| 市区町村 | 制度名 | 概要・採用サイトとの関連性 |
|---|---|---|
| 吹田市 | 中小企業ホームページ等作成事業補助金 | 市内の中小企業が新たにホームページを開設する際の経費を補助 |
名古屋で利用できる補助金・助成金
名古屋で採用サイト制作の費用が補助対象となる補助金・助成金の一例は、以下のとおりです。
| 制度名 | 概要・採用サイトとの関連性 |
|---|---|
| 中小企業デジタル活用支援補助金 | ・中小企業のDXによる生産性向上や経営課題解決を支援 ・「WEBサイト等の立ち上げにかかるデザイン料」「WEBサイト等に掲載する動画制作費用」が補助対象 |
採用サイト制作に補助金を活用する注意点

採用サイト制作に補助金を活用する注意点として、以下の3点があげられます。
- 必ずしも採択されるとは限らない
- 内容の改正など情報を確認しておく
- 報告後のタイミングで支給される
上記のポイントに注意して、補助金の申請手続きを進めましょう。
必ずしも採択されるとは限らない
補助金は、申請すれば必ず受け取れるわけではありません。
当然ですが、申請したすべての事業者に補助金を交付すると予算が足らないでしょう。そのため、各制度には公募期間が設けられ、期間中に申請した企業から支援に値すると判断された事業者だけが選ばれる審査が存在します。
審査員は、提出された事業計画書をもとに「社会や経済にどのような良い影響をもたらすか」などの観点を厳しく評価します。つまり、採用サイトの必要性や事業への貢献度などを計画書で論理的に説明できなければ、不採択となって補助金を受給できません。
一般的な補助金の採択率は、50%前後というのが実情です。
内容の改正など情報を確認しておく
補助金を申請する前に、内容の改正など情報を確認しておきましょう。補助金制度は国の政策や経済情勢の変化に対応するため、内容は頻繁に改正されます。
「昨年は、この条件で申請できた」「インターネットの記事にこう書いてあった」など、過去の情報が現在の公募で適用されないケースは多くあります。
補助金を申請する際は必ず制度を管轄する事務局の公式ホームページにアクセスし、最新の公募要領を確認してください。
報告後のタイミングで支給される
補助金の申請において、資金繰りに関わる最も重要な注意点は、原則として後払いである点です。補助金は、採択が決定したらすぐにお金が振り込まれるわけではありません。
まず、申請した事業計画に沿って採用サイトの制作などを自社の資金で完了させ、制作会社への支払いもすべて済ませます。その後、かかった経費の証拠書類をすべて揃えて事務局に実績報告を行います。報告内容が承認されて初めて、補助金が自社の口座に振り込まれる流れです。
つまり、事業の実施から補助金の入金まで数か月から1年近く、企業が費用を全額立て替える必要があります。事前に資金繰り計画を立てておかないと「補助金は採択されたのに事業が実行できない」などの本末転倒の事態に陥りかねません。
補助金の申請準備と並行して、自己資金の確保や金融機関からの融資など受給までの資金計画を立てておきましょう。
補助金を活用した採用サイト制作を成功させる制作会社の選び方

補助金を活用した採用サイト制作を成功させる制作会社の選び方として、以下の3つのポイントがあげられます。
| 選定ポイント | 重要である理由 |
|---|---|
| 補助金申請のサポート実績 | ・申請手続きは専門的で複雑なため、知識がないと不採択のリスクが高まる ・実績豊富な会社は制度の目的や審査のポイントを熟知している |
| 採用や事業への理解力 | ・補助金採択がゴールではなく、採用成功が本来の目的である ・事業を理解していないと、採用につながらないサイトができてしまう |
| 制作実績のデザインと品質 | 採用サイトの品質が低いと企業のイメージダウンにつながり、優秀な人材を逃す原因になる |
補助金で作成する採用サイトの効果を最大化するためにも、上記のポイントを確認して信頼できる制作会社を選びましょう。
補助金なしでコスパの高い採用サイト制作ならワンページ

採用サイト制作なら、ぜひワンページにお任せください。ワンページは、求職者に他とは違う圧倒的な情報量とクリエイティブで強い印象を与えられる採用サイトの制作が可能です。求人メディアでは伝えきれない貴社の働き方や社風を詳細に表現し、ミスマッチのない採用を実現できます。
また、ワンページはIndeedの正規代理店の経験もあり、蓄積されたノウハウを活かした採用サイト制作の実績も豊富です。そのため、貴社が採用で重視するポイントを求職者に響くコンテンツとして漏れなく発信できます。ワンページは業界最安値で採用サイトのテンプレートを用意しており、制作費を抑えやすい点もメリットです。
まずは、貴社の事業内容や採用に関する悩みをワンページまでお聞かせください。採用の成功につながる採用サイトの企画立案〜制作・保守運用まで、ワンストップで責任を持ってサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:補助金を有効活用してお得に採用サイトを制作しよう
IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金などの国の制度から、各地域が独自に設ける助成金まで多くの選択肢があります。しかし、申請すれば必ず採択されるわけではなく、原則として後払いであるなど注意点も存在します。
補助金を最大限に活用するための最も確実な方法は、経験豊富な制作会社をパートナーに選ぶことです。採用サイト制作と補助金申請の両方に精通した制作会社と連携すれば、採択の可能性を高めて時間と労力の削減につなげられます。
本記事を参考に補助金をスムーズに申請・受給し、コストを下げながら質の高い採用サイトを制作しましょう。









