「よくある質問(FAQ)の作り方とは?」
「良質なよくある質問を作成するコツを知りたい」
ホームページへのよくある質問の設置は、ユーザーと企業双方にメリットがあります。実際に、多くのサイトでよくある質問が導入されています。
しかし、よくある質問を新規で作成する場合、何から始めれば良いのか悩んでしまうでしょう。
そこで本記事では、よくある質問(FAQ)の作り方や良質なよくある質問を作成するコツを解説します。
この記事の内容
FAQとは?

FAQとは「Frequently Asked Questions」の略で、日本語では「よくある質問」として活用されます。企業が、顧客や社員から頻繁に寄せられる質問と回答をセットにして整理・公開するもので、ユーザーが知りたい情報にすぐアクセスできる仕組みです。
FAQは、主に次の3タイプに分類されます。
| 顧客向けFAQ | 商品やサービスに関するよくある質問をまとめたもの。公式サイトで公開され、誰でもアクセスできる。専門用語を多用せず、誰にでも分かりやすく記載されるのが特徴。 |
|---|---|
| 社内向けFAQ | 業務システムの使い方や社内ルール、人事・総務関連の情報などを共有する目的で作られる。ナレッジ蓄積による業務効率化が期待できる。 |
| オペレーター向けFAQ | オペレーターが顧客対応時に使用するマニュアル的なFAQ。応対品質の均一化や迅速な対応に役立つ。 |
適切なFAQの活用は、対応コストの削減だけでなく、業務の属人化防止やナレッジ共有の強化にもつながります。近年では、AIと連携したFAQシステムも増え、より効率的な運用も注目されています。
FAQとQ&Aとの違い

FAQとQ&Aは、いずれも「質問と回答のセット」という点で共通しますが、その目的や活用方法には明確な違いがあります。
FAQは「実際によく寄せられる質問」をもとに作られるのに対し、Q&Aは「想定される質問」も含めた情報提供に使われることが多く、マニュアルや資料の一部として使われるケースもあります。
以下の表で、それぞれの特徴を整理してみましょう。
| 項目 | FAQ | Q&A |
|---|---|---|
| 概要 | 実際に頻繁に寄せられる質問と回答のまとめ | 想定される質問と回答を含めた情報提供形式 |
| 情報元 | 顧客や社員からの実際の問い合わせ | 実際の質問や予想される内容を含む場合あり |
| 掲載範囲 | 頻出する質問のみを厳選 | 内容は広く、包括的に掲載することもある |
| 活用場面 | Webサイト・社内ポータル | マニュアル・ガイド・資料など |
| 目的 | 問い合わせの削減、業務効率化、CS向上 | 情報整理、理解促進、操作支援など |
FAQは、ユーザーの利便性を高め、問い合わせ件数の削減など業務改善にもつながります。一方、Q&Aは主に理解をサポートする補助的なコンテンツとして役立つでしょう。
FAQの基本構成・要素
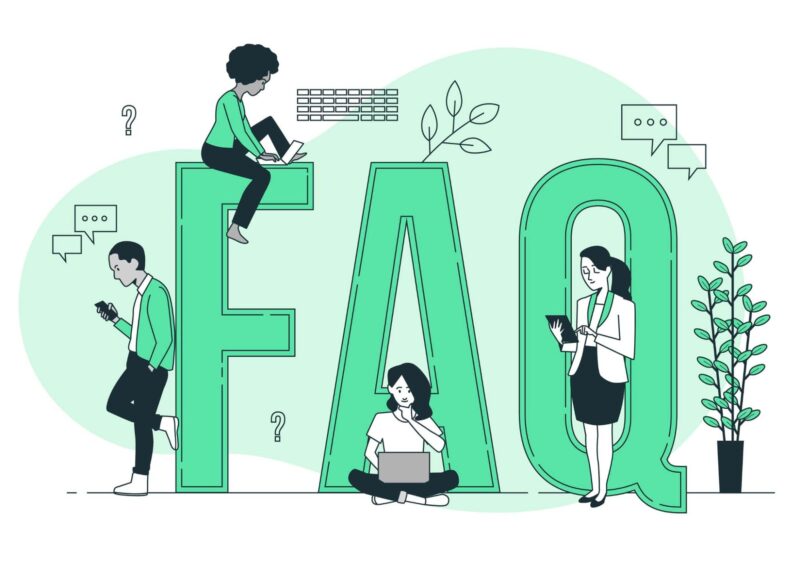
FAQは、ただ質問と回答を並べるだけではなく、ユーザーにとって「わかりやすく」「使いやすい」設計が求められます。
以下の4つの要素を押さえて構成すると、より効果的なFAQが完成します。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 質問文 | ユーザーが抱く疑問を端的に表現する。検索されやすいキーワードを含めるとより良い |
| 回答文 | 質問に対する明確な答えを簡潔に記載。情報量が多い場合は箇条書きや図表も活用する |
| 参考ページURL | 詳細情報や補足解説を記載したページへのリンク。ユーザーの深掘り行動をサポートする |
| 関連FAQ | 類似した質問へのリンクを設け、より多角的な解決策を提示できるようにする |
FAQの目的に合わせて必要な要素を組み込むと、ユーザー満足度の向上につながります。
FAQの作り方7ステップ

続いて、よくある質問の作り方を7ステップに分けて解説します。
- 質問の素材を情報収集する
- 多い質問項目を整理する
- 回答項目を作成する
- 記載すべき内容か精査する
- 顧客視点でFAQの見せ方を決める
- 作成したFAQを社内で確認する
- 公開したら定期的に改善する
質問の素材を情報収集する
まずは、質問の素材となる情報を集めましょう。
過去の問い合わせ内容やホームページ、仕様書などから、よくある質問となる情報を洗い出します。
多い質問項目を整理する
質問の素材を洗い出したら、質問項目を整理しましょう。
問い合わせ回数や頻度などを確認しながら、ユーザーのニーズが高い内容を中心に質問項目を整理します。
回答項目を作成する
質問項目を整理できたら、それらに対する回答項目を作成しましょう。
どんなユーザーが読んでも問題を解決できるように、専門用語は使わずわかりやすい表現で回答を作成することが大切です。
記載すべき内容か精査する
回答項目をひと通り作成したら、FAQに記載すべきかどうかを精査しましょう。
質問の中には、解決に高度な専門知識が必要なものなど、FAQに記載してもユーザーが解決できない内容も少なくありません。
顧客視点でFAQの見せ方を決める
FAQに記載する質問を決めたら、顧客視点でFAQの見せ方を考えます。
ユーザーがFAQを閲覧した時に、すぐ問題解決できるように、読みやすい文章やレイアウトを心がけましょう。
ページ内の情報が多く見えづらくなる場合は、関連FAQとしてページを分けたり、参考ページのリンクを設置してください。
作成したFAQを社内で確認する
一通りFAQが完成したら、社内で内容を最終確認しましょう。
情報の抜け漏れや誤りは、ユーザーからの信用を落としかねません。誤った情報を公開しないように、複数人できちんとチェックしましょう。
公開したら定期的に改善する
良質なFAQにするためには、公開後の定期的な改善が欠かせません。
FAQ公開後の問い合わせ数の増減や問い合わせ内容、ページのアクセス数をチェックして、ユーザーに適したFAQに改善しましょう。
定期的な改善を繰り返すことで、ユーザーの満足度を高める有益なFAQになります。
良質なFAQを作る5つのコツ

質の良いよくある質問を作るために、以下の5つのポイントをおさえましょう。
- ユーザー目線で作成する
- 関連項目のリンクを設置する
- キーワード検索欄を設置する
- 質問をカテゴリ分けして掲載する
- 悩み解決のためのチャットボットを設置する
ユーザー目線で作成する
よくある質問をユーザー目線で作成することが大切です。
ユーザー目線が抜けた状態でよくある質問を作成してしまうと、ユーザーが扱いづらい内容になります。
ユーザーに必要な情報をうまくピックアップし、誰が読んでも理解できるようなわかりやすい文章で作成しましょう。
文字だけでは伝わりづらい内容には、図解を用いた説明を取り入れてみてください。
関連項目のリンクを設置する
関連性のあるページ同士にはリンクを設置しましょう。
よくある質問の中で似た内容のページや、関連する内容のページにそれぞれリンクを設置すると、ユーザーの悩みを一気に解決できる可能性が高まります。
キーワード検索欄を設置する
よくある質問に、キーワード検索欄を設置することも大切です。
キーワード検索欄を設置することで、ユーザーが解決方法に辿り着きやすくなります。
キーワード検索欄はツールを活用すれば無料で設置できるため、積極的に設置しましょう。
質問をカテゴリ分けして掲載する
また、よくある質問が多ければカテゴリ分けして掲載しましょう。
対象となる層が求めている情報をすぐに見つけられるように、ユーザー目線でカテゴリを作成しましょう。
悩み解決のためのチャットボットを設置する
近年ではホームページ内に、チャットボットを設置する企業が増えています。
チャットボットとは「チャットに質問を入力する」「項目を選択する」だけで、対話形式での問題解決が叶う仕組みのこと。
チャットボットは、非常に取っ付きやすく、顧客が抱える悩みに対して適切な回答を導き出せます。
こうしたシステムの導入も、ユーザーの満足度を高める布石となるでしょう。
FAQを作成する3つのメリット

では最後に、よくある質問を作成するメリットを3つ紹介します。
- 問い合わせ業務を効率化できる
- 顧客満足度の向上につながる
- サイトのSEO効果を期待できる
問い合わせ業務を効率化できる
よくある質問を作成することで、問い合わせ業務を効率化できます。
ユーザーがよくある質問で問題解決できる分、問い合わせ件数を減らせるため、オペレーターの業務を減らせます。
問い合わせ業務を効率化できると、そこに割いていた人員を他の業務に回すことが可能です。
顧客満足度の向上につながる
よくある質問の設置は、顧客満足度の向上にもつながります。
よくある質問を公開しておけばユーザーの疑問をすぐに解決できるため、商品やサービス、会社全体のイメージアップにもつながるでしょう。
また、よくある質問の設置はユーザーの不満を減らすことにもつながるため、クレーム予防にも効果的です。
サイトのSEO効果を期待できる
よくある質問を設置することで、サイトのSEO効果を期待できます。
ユーザーが知りたい情報をうまく盛り込めると、検索エンジンからの評価を得られるため、検索結果の上位表示を実現可能に。
サイトを検索結果の上位に表示されれば、サイト全体のアクセス数増加にもつながります。
FAQの作り方で参考になる質問例

FAQの質問例を、カテゴリー別に分けて紹介します。自社の目的に合わせて、カスタマイズしてみてください。
- 顧客向け
- コールセンター・サポート担当者向け
- ECサイト向け
顧客向け
顧客向けのFAQで活用できる質問例は、以下のとおりです。
| カテゴリー | 質問例 |
|---|---|
| サービス内容・特徴 | ・〇〇サービスとは何ですか? ・〇〇と他社サービスの違いは? ・どんなメリットがありますか? |
| アカウント・登録 | ・アカウントの作成方法は? ・登録確認メールが届きません ・ログインできない場合の対処方法は? |
| 契約・料金 | ・契約プランの違いは? ・月額料金に含まれる内容は? ・料金の請求タイミングはいつですか? |
| 解約・キャンセル | ・サービスの解約方法を教えてください ・キャンセル料は発生しますか? ・途中解約した場合の返金は? |
| 技術的トラブル | ・アプリが起動しない時は? ・エラーコードXXXXが表示されます ・アップデート方法を教えてください |
| サポート関連 | ・問い合わせ方法を教えてください ・受付時間はいつですか? ・チャットサポートはありますか? |
| セキュリティ・プライバシー | ・個人情報はどのように扱われますか? ・セキュリティ対策は何をしていますか? ・パスワードの再設定方法は? |
作成時は、専門用語を避け、誰にでも伝わる言葉を意識してください。
また、回答の信頼性と正確性を担保し、定期的に更新しましょう。
コールセンター・サポート担当者向け
次に、コールセンター・サポート担当者向けの質問例を紹介します。
| カテゴリー | 質問例 |
|---|---|
| 応対マニュアル・フロー | ・クレームが発生した際の対応フローは? ・対応のトーン&マナーに決まりはありますか? ・謝罪文の書き方は? |
| エスカレーション対応 | ・上長へ報告が必要な判断基準は? ・エスカレーション時の記録方法は? ・二次対応はどこへ引き継ぎますか? |
| ツール・システムの操作 | ・CRMの入力方法は? ・FAQシステムの検索方法を教えてください ・画面がフリーズした際の対応は? |
| 情報管理・セキュリティ | ・顧客情報の保存期間は? ・個人情報の取り扱いルールは? ・通話録音の保存ポリシーは? |
| よくある問合せ対応 | ・「届かない」「使えない」などの問い合わせが来たら? ・FAQにない質問をされたらどうする? |
| スクリプト・ナレッジ共有 | ・最新のトークスクリプトはどこで確認できますか? ・オペレーター間で知見を共有する方法は? |
作成時の注意点として、見やすく要点を絞った構成にしましょう。
業務フローや操作マニュアルは、図解や箇条書きを使って分かりやすく、システムやルールが変わった場合、即座に更新できる体制があると安心です。
ECサイト向け
ECサイト向けに活用できる質問例は、以下のとおりです。
| カテゴリー | 質問例 |
|---|---|
| ご注文について | ・注文確認メールが届きません ・注文内容を変更したい場合の手順は? ・注文をキャンセルしたい場合は? |
| お支払い方法 | ・支払い方法には何がありますか? ・決済後の支払い方法変更は可能ですか? ・領収書の発行はできますか? |
| 配送について | ・いつ届きますか? ・配送業者を指定できますか? ・追跡番号の確認方法は? |
| 商品について | ・サイズやカラーの違いはありますか? ・素材やお手入れ方法は? ・商品に不備がある場合はどうすれば? |
| 返品・交換・キャンセル | ・返品の条件を教えてください ・サイズ交換は可能ですか? ・商品到着後、何日以内なら返品できますか? |
| アカウント・会員登録 | ・会員登録の手順を教えてください ・パスワードを忘れたらどうする? ・退会手続きはどこから行いますか? |
| ポイント・クーポン | ・ポイントの使い方は? ・有効期限はありますか? ・クーポンコードの入力ミス時の対応は? |
| サイト利用・不具合 | ・商品がカートに追加できません ・エラーが表示されて進めません ・スマホで表示が崩れる場合の対処法は? |
作成時は、購入前と購入後のユーザーの不安や疑問に応える内容を優先的に記載しましょう。
回答が長くなる場合は、箇条書きやリンクを活用して視認性を確保すると親切です。
まとめ:FAQのの作り方を活かしてユーザーファーストなホームページを目指そう

良質なよくある質問を設置することで、顧客満足度を高められるほか、業務効率化も図れます。ユーザー目線を忘れずによくある質問を作成し、ユーザーファーストなホームページを目指しましょう。
ワンページ株式会社では、Web制作から集客施策まで包括的な支援を行う制作会社です。
ユーザーからのよくある質問をもとに解決に導くページデザインを提案・制作させていただきます。
ホームページやよくある質問ページの制作でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。









